ファンモーター 風量-静圧特性
圧力損失
空気をある流路の中に流そうとした場合、その流路の中にはその流れを妨げる向きに送風抵抗が発生します。
例えば下図の場合で比較しますと、上の装置内はほとんど空洞のため送風抵抗も小さく、風量の減少はあまりありません。しかし、下の装置内のように風の流れを妨げるものが多くなると、送風抵抗は増大し風量が減少してしまいます。
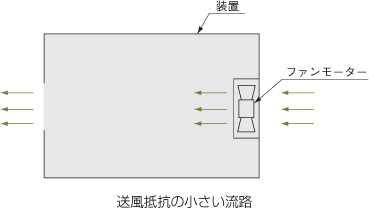
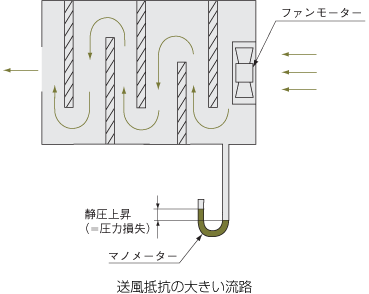
このことは、電流の流れにおいてインピーダンスの小さい場合には大きな電流が流れ、インピーダンスの大きい場合には電流が小さくなることと非常によく似ています。この送風抵抗は、装置内の静圧を上昇させる圧力のエネルギーとなり、圧力損失と呼ばれ次のような式で表されます。
- V
- 流速[m/s]
- ρ
- 空気の密度[kg/m3]
- ζ
- 管路固有の抵抗係数
- A
- 管路の断面積[m2]
- Q
- 風量[m3/s]
この式はファンモーターの方から見ますと、ある風量Qを流すためには装置の中の圧力を式(1)Pだけ上昇させることのできる静圧をファンモーターが持っていなければならないことを意味しています。
風量―静圧特性
ファンモーターの特性は一般に、ある風量を出そうとしたときの静圧値との関係を示した風量―静圧特性によって表されます。例えば必要とされる風量Q1で、そのときの装置の圧力損失がP1であるとします。次の図に示されたファンモーターの特性の場合、ファンモーターの持っている静圧値はP2であり、必要とされる静圧値P1よりも大きいため十分に必要とする風量を得ることができるわけです。
圧力損失は風量の2乗に比例しますので、風量を2倍にする場合には、単に風量が2倍あるだけでなく、同時に静圧が4倍あるファンモーターを選定する必要があります。
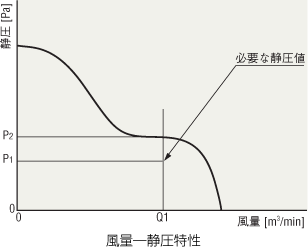
風量―静圧特性の測定方法
風量―静圧特性の測定はピトー管による風洞測定方法と、ダブルチャンバーによる測定方法の2種類があります。
このうちダブルチャンバー方式の方が風洞方式に比べ精度が高く、海外でも広く用いられていることから当社ではこの方法を採用しています。
また、当社の測定装置は世界でも広く認められているファンモーター測定方法の規格である、AMCAスタンダード210に基づいています。この方法は下図に示すように、ノズル前後の差圧ΔPと、チャンバー内の圧力Psを測定することにより、被測定ファンモーターの風量―静圧特性を求めるものです。
(AMCA : The Air Moving and Conditioning Association )
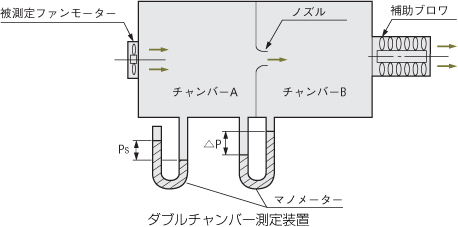
当社のダブルチャンバーは、ファンモーターに吸込み管、吐出し管があるなしにかかわらず使用することのできる、最も汎用性の高い測定装置です。
この方式では、チャンバーAとチャンバーBの圧力の差からノズルを流れる流体の速度を求めることができるため、風量Qはノズルを流れる速度V、ノズル面積A、流量係数Cとの相乗積として表すことができ、以下式(2)のようになります。
- A
- ノズルの断面積[m2]
- C
- 流量係数
-
\(\overline{V}\)
- ノズルの平均流速[m/sec]
- ρ
- 空気の密度[kg/m3](20℃ 1気圧のとき ρ=1.2[kg/m3])
- ΔP
- 差圧[Pa]
風量―静圧特性の測定にあたっては、補助ブロワを用い、チャンバーBの圧力を制御することによりチャンバーAの圧力を変え、特性曲線上の各ポイントを測定することができます。また、当社ではコンピュータと連結させることにより短時間で、しかも高精度な測定を可能としています。