1-4. ACモーターの動作原理2(回転磁界)
1-4-1. アラゴの円板からステーターとローターへの置き換え
アラゴの円板を、ACモーターの内部構造に置き換えて説明します。
ステーターは、N極・S極の電磁石のモデルに。ローターは、長方形のコイルのモデルに変換して考えます。
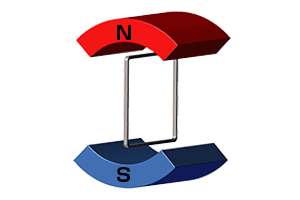
| 右手の法則 | ①磁束が発生 (ステーターに電流が流れる) |
+ | ②導体が移動 (ステーターとローターの位置が変化) |
|---|---|---|---|
| || | |||
| ③誘導電流が発生 (ローターに誘導電流が流れる) |
|||
| 左手の法則 | ④磁束が発生 (ステーターに電流が流れる) |
+ | ⑤誘導電流が発生 (③の結果) |
|---|---|---|---|
| || | |||
| ⑥力がはたらく (ローターが回転する) |
|||
| 右手の法則に従い、コイルに誘導電流が流れる | 左手の法則に従い、コイルが回転する |
|---|---|
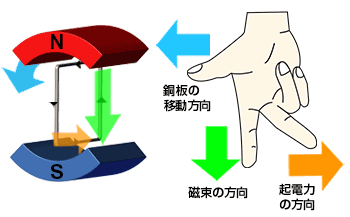 |
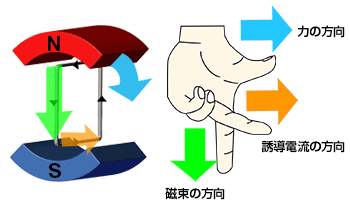 |
閉じたコイルを磁界の中に置き、外側の磁石を時計方向に回転させます。
すると、コイルに誘導電流が流れます。電流が流れると、磁界と作用してコイルに力が発生ます。
1-3. ACモーターの動作原理1(アラゴの円板)と同じように、コイルは磁石と同じ方向に回転を始めます。
実際のローターは、回転力を効率よく取り出せるよう、複数のコイルが重なり合っています。
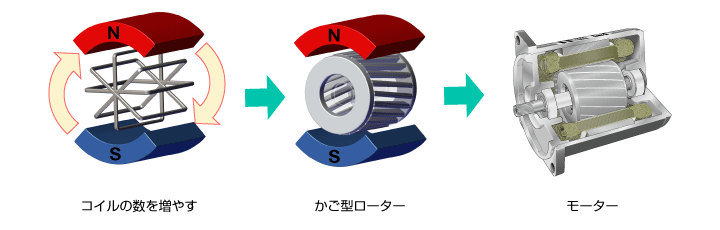
アルミと鉄を使い、複数のコイルが重なり合ったローターを、かご型ローターと呼びます。
かご型ローターでは、アルミ部分に電流が流れます。
1-4-2. 回転磁界(単相電源・三相電源)
ステーターがローターの周りを回転することで、ローターが回転します。この回転する磁界を回転磁界と呼びます。
ACモーターがどのように回転磁界を発生させているのか、説明します。
単相電源の場合―コンデンサを利用した位相のずれ
単相電源で駆動するモーター内部には、主巻線と補助巻線の2つの巻線があります。
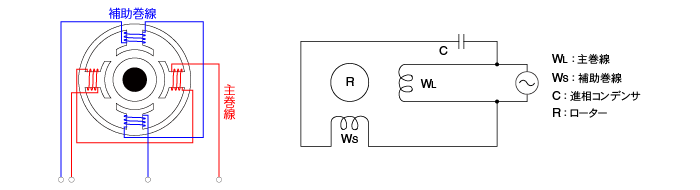
主巻線は電源に、補助巻線はコンデンサを介して電源に接続します。
主巻線には電源からの電流が直接流れます。対して、補助巻線にはコンデンサを介した電流が流れます。
単相電源で運転する場合には、進相コンデンサを使ってニ相電源に近い波形を作り出し、回転磁界を発生させています。
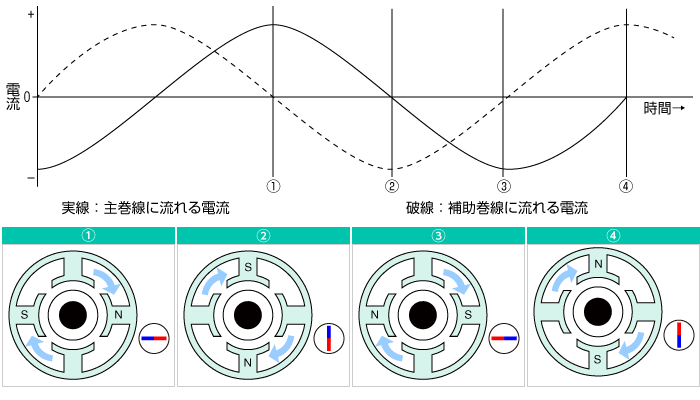
単相電源を接続すると、①~④の現象を繰り返します。
- ①
- 主巻線に電圧がかかり、補助巻線には電圧がかかりません。主巻線の磁極に、N極とS極が発生します。
- ②
- 補助巻線に電圧がかかり、主巻線には電圧がかかりません。補助巻線の磁極に、N極とS極が発生します。
- ③
- 主巻線に電圧がかかり、補助巻線には電圧がかかりません。主巻線の磁極に、①のときと反対の磁極が発生します。
- ④
- 補助巻線に電圧がかかり、主巻線には電圧がかかりません。補助巻線の磁極に、②のときと反対の磁極が発生します。
このように、ステーターに発生する磁界は、右向きに回転するように変化します。
関連情報
ACモーターの取り付け、配線について、当eラーニングの後半に動画をご用意しています。
三相電源の場合―電源の位相のずれ
単相モーターでは、主巻線、補助巻線の2つの巻線がありましたが、三相モーターでは3つの巻線で構成されています。
それぞれ電源側をU、V、Wとすると、U-V間、V-W間、W-U間の3通りです。これらの巻線を、電源に直接接続します。
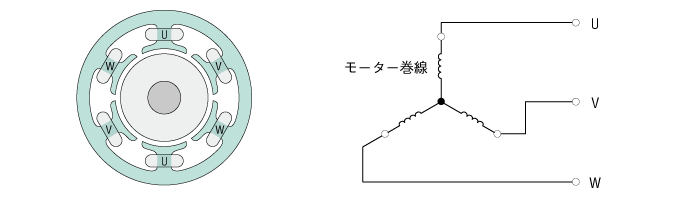
三相電源のU・V・Wの電源ラインでは、位相が120°ずれています。
この位相のずれを活用して回転磁界を作り出すため、単相のようなコンデンサの接続は不要です。
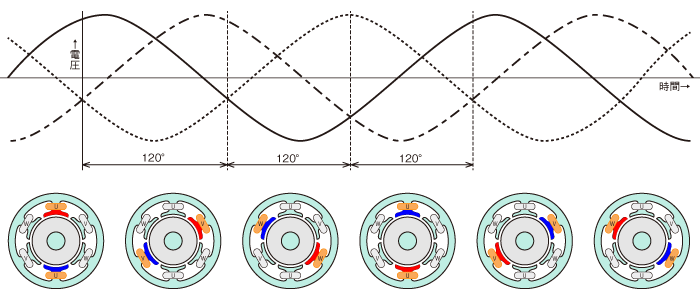
関連情報
ACモーターの取り付け、配線について、当eラーニングの後半に動画をご用意しています。
まとめ
ACモーターは、ステーターに回転磁界を作り出すことによって回転する。
単相電源は、コンデンサの接続によって二相電源に近い波形を作り、回転磁界を発生させている
三相電源は、もともと位相のずれをもつため、直接電源に接続するだけで回転磁界が発生する
内容についてご不明点はありませんか?お気軽にお問合せください。
- WEBテクニカルサポートに
メールするメール開封後、内容を確認し、当社よりご連絡いたします。
なお、お問い合わせの内容によっては、お電話をさしあげる場合がありますのでご了承ください。 - お客様ご相談センターに
電話する